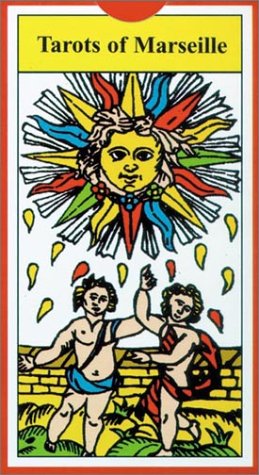タロット象徴事典 用語解説
特筆すべき用語解説集
先史時代の祈祷、呪術
人類史を辿れば、先史時代のB.C.15000年の壁画が、呪術的な儀式を司る美術家兼、呪術師、祈祷師が存在していた可能性を私たちに伝えています。それは、氷河期を経て、ユーラシア大陸とアフリカ大陸が形作られ、現在の地上と似通った気候になった頃、地中海沿岸西部のアルタミラ、また、ラスコー洞窟をキャンバスに現存しているものです。壁画の中には、角と尻尾をつけた人間の絵などもあり、魔術儀式の情景が描かれたものであろうと考えられています。壁画が多く残っている地中海沿岸の西部では、主に狩猟、植物の採集が営まれ、東部では、人々が集落を作り定住を始めていました。出土品には埋葬品が多く、死者の魂を弔う習慣があったこと、祖先崇拝の観念を育てていたことが判明しています。
シュメール人の多神教
シュメール人が残した「神名」の断片が、シュメール人の多神教の最古の物証と言えるようです。そこには数千にも及ぶ神の名前が記されていること、しかし、中には重複する名前もあることがわかっていますが、シュメール人は、様々な神を信仰する多神教の民族であったこと、主神の名前が、政治的な動向に連れて移り変わっていることなどが判明しています。
チグリス川とユーフラテス川流域に発祥した最古の文明、メソポタミア文明は、シュメール人によるものです。諸説がありますが、彼らはメソポタミアの先住民ではなく、B.C.3500年頃来住した民族であるとも推定されています。
現代社会において、「神」「宗教」「崇拝」といったテーマは特異なものとして扱われる風潮がありますが、この当時に生きた原始人たちとっては、どうだったのでしょうか。思うに、彼らはただ落ち着いて、安定した暮らしを一様に望んでいただけなのでしょう。想像してみて下さい。高度な技術もない未開の地で、つたない農業、狩猟を用いて今日明日の命をつないでいた古代人にとって、身近な存在がいつか忽然【こつぜん】と、姿を消して居なくなるやもしれないという不安や恐怖は常につきまとっていたはずです。大自然の脅威を克服することができない人間の限界を痛いほど思い知らされながら、どうしたら穏やかな安定した暮らしが営めるかということを、最重要事項として暮らしていたに違いありません。人類史は、神や宗教の概念と共にスタートしたと言っても過言ではないでしょう。神という絶対的、超自然的存在、宇宙を司る大いなる創造のエネルギーを確信せざるを得ないような太古に生まれた人々の意識が、祈りの儀式を、天体観測を、文字や絵を、神話を起こし文明を発祥させたといえるのではないでしょうか。
エジプト人の宗教、魔術
古代のエジプト人たちすべてに、必ずしも一定の信仰があったわけではないようですが、霊魂不滅と来世についての思想を発達させた民族として伝えられています。たとえ肉体が朽ち果てても魂は生き続けると信じ、死後は、大空の向こうにあるだろう天界に迎え入れられることが、彼らの最大の願いだったのです。
「エジプトはナイルの賜」というヘロトドスの名言は有名ですが、エジプト人が生きるも死ぬも、ナイル川にかかっていたという点は重要です。他地域を圧倒する肥沃なナイル川ですが、一度【ひとたび】川が氾濫すれば、流域に住むエジプト人は文字通りすべてを失ったのです。自然の摂理を把握し、その脅威を乗り越えたいと、彼らはどれだけ願ったことでしょうか。天文観測と占星術との起源がひとつであることを、今やご存知の方も多いでしょう。
エジプト人は、宇宙を司る神を信じ、動物や植物、天体を神に見立てる宗教を生み出し、文字を発達させると共に書物や物語を通じて、宗教の文化を広げていきました。安定した生活と幸せを感じて生きるために、人々は日常的に神に祈りを捧げ、宗教の一部として、護身のための魔術儀式を編み出したのでした。当時、人を呪うような悪しき魔術の使い方は既に禁止事項として定められていたと言われています。
死者を埋葬する儀式にはことさらにエネルギーが注がれ、埋葬品が来世においても役立つような魔術が執り行われていたとも言われています。また、死体や墓はその置かれ方には一定の方向性が見出されていることなどから、方位についての吉凶の観念が育っていたことが伺え知れます。
古代史の研究調査は引き続き日進月歩です。天地を包括する宇宙、その宇宙を司る神の存在を信じ、神の力を全身で授かろうと多大なエネルギーを費やしていた当時の人々の実態が、今後も明らかになっていくことでしょう。
ギリシア・ローマ神話
古代ギリシアにおいても、多神教が信仰されました。紀元前5世紀頃、第一期ミノス文明を経て、第二期ミュケナイ文明の時期に入ると、神殿と、各神殿にまつわる様々なギリシア神についての様々な物語が確立されます。中でも、ギリシアのテッサリア地方にあるオリンポス山を中心に展開された、オリンポス十二神の物語は有名です。主神ゼウスの系譜を中心に、おびただしい数の神々についての信仰、神話が確立され、その後勢力を持ったローマ人たちに受け継がれていきます。いわゆる「ギリシア・ローマ神話」は、ローマ帝国時代の紀元前2世紀頃までに体系化されています。神話における神は不死身とされていますが、当世の人々になぞらえた喜怒哀楽の激しい情感豊かな人格を与えられているのが特徴です。
密儀宗教
広く世に知れ渡った一般的な宗教に対して、むしろ一般社会にはそう簡単に公にならぬようと、守られ維持存続に努められていた「密儀宗教」がギリシア時代に派生し、ローマ帝国時代に至っては全盛期を誇っています。新規参入者に対する秘密の参入式(イニシエーション)から段階を追って構成されている階級制度の下に、組織化されていることが密儀(Mythtery)の前提であるとされています。この参入式が、元来の宗教的儀式である「洗礼」といったタイプのものではないことが核心なのではないかと筆者は考えています。代表的なものに、アテナイで盛んに行われていた「エレウシスの密儀」などがあります。主神や太陽神、光の神として崇められていた神々ではない神、女神イシス、ディオニュソス、ミトラ、セラピス、ユピテルなどが、主神の盲点を補える存在であるが故に、光の統治しない側面を司るその性質故に、むしろ絶対神にも勝るとも劣らぬ存在として一部の熱狂的な信者を集め、流行するに至るのでした。新興宗教やカルト教団の先駆けとも言えるのではないでしょうか。
エトルリア人の卜術
B.C.1~2世紀、ローマ人に吸収されてしまった民族で、もともとはイタリア半島の先住民であったとされるのがエトルリア人です。彼らが、B.C.6~5世紀に建国したフィエゾーレという町は、現在のフィレンツェの「母」に喩えられ、その伝統文化と共に今日においても歴史家、美術家に注目される場所となっています。エトルリア人独自の神々が祀られ、彼らを征服したローマ人が、これらを土台にローマの神々を創り上げたという側面もあるのです。
彼ら独自の文化として、卜術【ぼくじゅつ】がよく取り上げられますが、これはシュメール人から受け継いだ文化であるとされています。道具を使って、出目によって吉凶を判断するタイプの占いが卜術【ぼくじゅつ】です。当時の主な占法は、神への生け贄として捧げられた動物の肝臓の状態から、何らかの予兆を得るものでした。予兆を解釈するためには、エトルリア人の神について、宗教書をマスターしなければならなかったのです。エトルリア人の中には、これを専門に学び修行をした臓卜師が存在しており、卜術は、身分の高い家柄において世襲で伝えられる「家宝」でもあったのです。ギリシア人、ローマ人共にこの術を重んじ、古代ヨーロッパ社会において、臓卜師はたちまち一定の地位を授けられたとのことです。臓卜師の修行に使用されたとされる、ブロンズ製の肝臓の模型が出土しています。これに似た粘土製の羊の肝臓模型が、B.C.18世紀のメソポタミア地方からも出土しています。
かのルネッサンス芸術のパトロンとして名を馳せるイタリア、フィレンツェ共和国を司ったメディチ家は、彼らがエトルリア人の血を引く一族であることをことさらに強調し、エトルリア出土の芸術作品を好んで集めていました。実際には、メディチ家がフィレンツェ北方のムッジェロ渓谷の出であることはわかっています。メディチの語源は、英語の薬/Medicine等と同様、ラテン語の「医者、医療」であり、彼らが医療に関わりの深い一族であるとされていますが、フィレンツェの医師・薬種商組合の名簿にはメディチ家のメンバーが見あたりません。原始的な医術に関わりのある一派を祖先に持つことの表れなのかもしれません。
ケルト人の宗教、口頭伝承
ヨーロッパ広域に渡って、B.C.900年頃から広く分布していた先住民族です。彼らの拠点は、現在のフランスの位置にあるガリアであり、ローマ人からはガリイと呼ばれ、その荒ぶる攻撃性が恐れられていた民族です。ローマ帝国の総督カエサルが自ら記した『ガリア戦記』において、ガリア人の民族的な特徴が報じられています。ガリア人=ケルト人は、B.C.50年、ローマ軍に破れ、その支配下に入ります。
それ以前に、ケルト民族の地には、キリスト教の布教活動も盛んに行われていました。元々のケルト人の宗教においては、崇拝の対象となる特定の「神」は存在しません。彼らは、森羅万象(宇宙に存在するあらゆるものの総称)を崇めていたのです。太陽に始まり、大地から石から動物たちまで、自然界に存在するあらゆる物の人間を超越した力を脅威として恐れ敬い、万物に生かされていることを大前提に生活したのです。樫の木が生い茂る深い森林に居住していた彼らは、樹木崇拝の先駆者でもありました。
ケルト社会は、魔術師(ドルイド)、騎士(ナイト)、平民の三つの階級で構成されていました。最も有力な存在は、祭司として国政をも司る魔術師でした。先導者の象徴として聖なる樹木で作られた杖を持つケルト人の魔術師の姿は、古今東西の童話に見られる「魔法使いの杖」の起源と言えるのかもしれません。
騎士階級は、戦士貴族とも呼ばれ、ケルト人の中でも英雄的な存在でした。そもそも、ケルト人は、馬に乗り、剣をたくみに操ることについて、他民族から一目置かれている。B.C.1世紀頃登場した騎馬民族の流れを汲むケルト民族であると考えられますが、野生馬を飼い慣らし戦闘機として使いこなすという技術の発達は、古代史上の革命的なできごとだったのです。ギリシア、ローマなど周辺の民族から恐れられたケルトの騎士にまつわる英雄伝説から、「聖杯伝説」「アーサー王物語」が誕生し、世界中で愛読されています。物語の端々に脈打つケルト人の精神は、中世ヨーロッパ社会に注目された道徳的な規範「西洋騎士道」として蘇【よみがえ】ったのでした。
ケルト人は、文字を使用していませんでした。魔術師は、神の世界、死後の世界について、また天体の運行などなど自然学を説く「知の教師」でもあり、それらを口頭伝承(口伝え)で後世に授けたのでした。騎士階級に属する吟遊詩人(バルド)は、騎士の活躍を歌にして語り歩き、ここからケルト民族独自の神話が創作されたものと考えられます。
エジプト人同様、霊魂不滅の観念を唱えたケルト人でしたが、彼らにとって、死は長い眠りに就くことでした。そして、肉体が朽ちても、魂はまた別の肉体に宿ると考えたのでした。故に、ケルト人は、死を恐れなかったことなども伝えられています。そこへ流布してきたキリスト教を、ケルト人は彼ら独自の解釈で取り入れ、オリジナルのシンボル、ケルト十字を創り上げたのでした。
ヨーロッパ文化の土台を形成するとされるユダヤ・キリスト教的なヘブライズムと、ギリシア的なヘレニズムという二本柱の狭間で、「教義」に依存せず、現実的に説明できない不可思議な現象を認め、目には見えない神秘の力を受け入れ、独特の世界観を作り出した民族が、ケルト人だと言えるでしょう。
現存する最古のタロット、ヴィスコンティ版で知られるヴィスコンティ一族が統治したミラノは、ガリアのインスブレース一族が起源であると伝えられています。
宮廷魔術師
ローマ帝国崩壊以降、文化の中心的役割を果たすキリスト教の勢力が強くなるヨーロッパでは、魔術や祈祷、占術などが教義に反するものとして、いっせいに排除されようとしていきます。俗に言う「魔女狩り」によって、15~18世紀には、実際には何の関係もない一般市民までがとらわれ、処刑されたという痛ましい歴史があります。一方で、力のある魔術師は、宮廷や王侯貴族に仕え、時には政局を占い、政治に口添えするようなことがあったことも史実として伝えられています。有名な宮廷魔術師に、フランスのヴェルサイユ宮殿に仕えたカリオストロ伯爵などがいます。
次第に、見せ物的な妖術、トリックをショーとして演じるエンターテイナーとしてマジシャンが登場するに至ります。中には、その術を悪用し、人を騙【だま】して小金を稼ぐような、ペテン師も存在していたことでしょう。アルカナ「正義」を経て、「吊された男」で、彼の行為に裁決が下るようなストーリー仕立てのタロット解釈も面白いものです。王に仕える存在として、アルカナ「愚者」では、宮廷道化の存在もお伝えしています。22のアルカナを、「愚者」=トリックスターの異相と解釈するのも興味深い試みでしょう。
フルール・ド・リス
「フルール・ド・リス Fleur de lis」は、フランス王国の「トゥールーズの聖ルイ」と呼ばれたルイ9世(Saint Louis1214~1270)が用いはじめたもので、1179年以降、正式にフランス国家の紋章となり、以来ルイ9世の花としてもヨーロッパでは馴染みのあるシンボルとなっています。その後、ルイ11世がメディチ家に許可し、イタリアのトスカーナ州、そしてフィレンツェ市の紋章もこれに準じたものとなり、やがてイタリア全土に見られるようになります。これらは実際には、アイリスであるとかアヤメやハスの花であるとも言われることもしばしばあります。三枚の花びらは三位一体というキリスト教的な象徴としても知られている一方で、槍の先の部分にも似ていることから男根と武力を象徴するものだとも考えられています。
エステンシ・タロットとフルール・ド・リス
このデッキは、当初札が発見されたフランス王国の国王シャルル6世(CharlesⅥ1318~1422)のために作られたものだと考えられましたが、絵札に見られるフルール・ド・リスが、もともとルイ9世の花であり、同じフランス王国といえども、南部に位置するトゥールーズと、パリなどを中心とする北部の美術や文化には大きな違いがあったことが指摘され、また、フルール・ド・リスの紋章がイタリア、フィレンツェ地方で頻繁【ひんぱん】に見られることなども考慮され、後になって、このデッキは年代的にももっと遅れて1400年代のイタリアで作成されたものだと考えが改められたのでした。
関連アルカナ・女教皇
十字、及び十字架
キリスト教起源だと思われがちですが、起源は古代に遡り、未だ解明されていません。十字、即ち交差する二本の線とその延長上にある四点とは、空間に導入された四方向、東西南北などの位置、方向性の関係が示され「宇宙」そのものを示す図形であるということは、専門家の間でほぼ一致しているようです。
アフリカでは、招霊の魔術が十字路で行われていたという記録があり、これは、霊たちがどの道に進むべきかの判断ができなくなるため、その場で身動きできないまま止めておくためであったとのこと。
マヤの古代都市パレンケの遺跡には、葉が生い茂る木のように見える十字架、即ちマヤ人たちの宇宙樹が描かれています。
ローマ時代には、重罪人の処刑道具として、縦横の長さが等しい二本線を交差させただけのシンプルな十字で、ギリシア十字と呼ばれるものが使用されていました。それに対して、横木よりも軸木が長い十字は、手を広げて磔【はりつけ】にされたキリストの全身像に由来したものでラテン十字と呼ばれ、キリストの死を連想させるために使用することが控えられ、交差する縦横の枝木に角度がついた変形タイプが好まれて使用されていました。
十字の種類
十字にも様々な種類があり、世界各地で、元々の「宇宙、四方位」という象徴的意味をもつものを原型として、様々な特徴のある変形十字へと派生が広がり新しいタイプの十字が生まれ今に至ります。
ウェイト版においては、「女教皇」「審判」に見られるギリシア十字、「皇帝」に描かれているアンク十字、「法王」の三つの横木が交差する三重十字、または教皇十字、「吊された男」の足形に暗示されているまんじなど、様々な観点から宇宙を考察しようとしたウェイト博士の功績を感じる部分です。
キリスト教
紀元前から今世紀に至るまでの壮大な歴史を背負った世界的教団として、その名は世界で知られています。筆者のことばで端的に述べさせていただくと、キリスト教とは、ユダヤ教に対抗して、あるいはユダヤ教から枝分かれする形で、徐々に確立していった宗教組織で、B.C.4年頃に登場した救世主・イエスにより、集中的に組織化、布教活動が広まり、ローマ帝国時代に一定の地位を確立するに至った世界宗教です。
紀元に入り、地中海沿岸一帯に広がる大規模な帝国と化したローマ帝国ですが、皇族たちの治世は乱れ、日常に不安を感じ、救いを求める民衆の声も高まりを見せていました。圧政、及び皇帝崇拝に反発したキリスト教徒は、帝国内で迫害を受けながらも、隣人愛と清貧を説き、社会的弱者が希望の光を見出せる教義を展開し、「庶民の味方」として根強く支持され、信徒を獲得していきます。やがて、その衰えることのないキリスト教に対する人気は、むしろ政治的に利用価値のあるものとして時の権力者により注目されるようになります。ついに313年、コンスタンティヌス帝がキリスト教を公認することを発表(ミラノ勅令)。教会が被った迫害による損害に対して国家賠償が支払われるに至ります。392年には、テオドシウス帝により国教と定められます。以降、教会には、国権による経済的にも保護されるようにまでなりますが、一方で、教会内の変質と人道主義の堕落をもたらすことにもなったと言われています。
その後はローマで採用されていたユリウス暦がキリスト教色に染められていきます。イエス・キリストの誕生年が西暦元年に、イエスが復活した日曜日が安息日に定められるなど、キリスト教は暦を通じて、世界に対する影響力を強め、キリスト教を抜きにして世界史を語ることはできないほどになるのです。
キリスト教の中にも様々な考え方、宗派があり、当時から今に至るまでに、いくつかのキリスト教諸教派が確立されています。父なる神、子なるイエス・キリストと聖霊との三位一体を信仰の対象とする考え方が多数を占めているようです。
新約聖書
キリスト教徒は、救世主イエス・キリストの教えを支持し、その教義と活動内容がまとめ上げられた「新約聖書」を教典とすることを定められています。主に、イエスの弟子たちによる記録として様々な書物が作成されており、当初ヘブライ文字で書かれていましたが、イエスの死後、1~2世紀頃までにまとめあげられました。
300年代のコンスタンティノープル公会議、ニケーア公会議を経て、神とイエスの立場が整理され、5世紀には、唯一神に三つの異相があること、即ち父なる神、子なるイエス、聖霊の「三位一体説」が正統とされ、聖書も正典、外典、儀典に分類されました。これをもって、現在の形の「新約聖書」が成立したのでした。現在日本に多く出回っているのは、ギリシア語に翻訳された聖書の英訳書の対訳本がほとんどであるようです。
旧約聖書
原本であるヘブライ語正典は、B.C.10世紀頃から編纂が始まり、A.D.1世紀末頃に完成している。「新約聖書(The New Testament)がキリスト教の教典であり、旧約聖書(The Old Testament)はユダヤ教の教典である」と言われることがありますが、厳密には正しくありません。どちらも聖書(The Bible)の内の、ひとつは古い(old)部分、ひとつは新規(new)の部分として、人間と神との契約を物語った書物であり、本来2冊でひとつの聖書なのです。聖書の旧約部分と新約部分とを、それぞれどう扱うで、キリスト教徒の中にもさらに派閥が存在しているのです。
確かに、旧約聖書(old)の最初の五書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記は、ユダヤの教典から借りてきた部分であるが故に、旧約部分はユダヤ教の教典であると誤解されるのでしょうが、単に、旧約部分とは、主イエス・キリスト生誕前の、天地創造説に始まる神と人間とのドラマであるだけです。そして、この部分に伝えられる前提に則って、新約部分のストーリーが展開されていくのです。また、ユダヤ教とキリスト教が、同じ旧約聖書を教典にしているとも考えるのは間違っています。それぞれの解釈で、別々の旧約聖書が存在し、ユダヤ教徒の聖典は「タナハ(もしくは、タナク)」と呼ばれています。「オールド・テスタメントThe Old Testament」と称される旧約聖書は、紛れもなくキリスト教徒のものなのです。
イエス・キリスト
キリスト教創始者の呼称。英語では、Jesus the Christ と表記されていますが、元々の呼称は、「エホバ(※)を助ける者」を意味するヘブライ語で書き表されています。
※旧約聖書に登場する神名ヤハウェYahwehの別称が、エホバJehovah
キリストChristとは、ギリシア語のkhristosが語源であり、ヘブライ語の「メシア=救世主」に当たることばで、「油を注がれた者」をも意味することばです。イエス・キリストを直訳すれば「油を注がれし救世主・イエス」となり、彼が清めの香油によって洗礼を受けた救済者として認識されていたことがわかります。そして、「クリスチャン」とは、油を注がれた者の派閥であることが伺い知れます。
そもそも、紀元前1300年頃、もともとメソポタミアの遊牧民であったヘブライ人が、イスラエルからエジプト領域にまで移住していく中で、ファラオの支配下に置かれたことから、自由な人生を奪回するための祈りから生まれたヘブライ人の宗教がユダヤ教です。唯一神・ヤハウェを信仰するこの一神教においては、現世における悲しみ、苦しみを克服するため、無我の境地に至ることが説かれ、精神的にも肉体的にもきびしい修行が信徒に促され、姦通罪なども適用され、その厳しい戒律に精通した者だけが救われるという禁欲主義と戒律主義を極めたものでした。
そんな中で、紀元前6世紀頃から既に旧約聖書の編纂が始まっていることが伝えられています。ユダヤ教の教義を下地に、新しい教えの書が確立されようとしていたのです。イエスは、自由、平等、愛を説き、娼婦でさえも救われると、社会の格差に寄らず教えを信じる者は救われるということを説き、支持者を集めます。イエスの死後も、弟子達は布教活動に没頭し、エジプト、ギリシア、ローマ一帯で信者を獲得していきました。ユダヤ教に取って代わるように台頭したのが、キリスト教なのです。
関連アルカナ・法王
ローマ教皇、及びローマ・カトリック教会
アルカナ「法王」のタイトルは、ウェイト版では「The Hierophant」ですが、「The Pope=ローマ教皇」になっている札も多く存在しています。
ローマ帝国で、国教と定められたキリスト教は、その後着々と政治権力と結びついてゆきます。帝国内では徐々に統治力が弱まり、西側と東側のそれぞれに皇帝が擁立され、政治的な対立が強まる中、キリスト教も、西側の「カトリック教圏(普遍)」と東側の「正教圏(オーソドックス)」とに別れ、たがいに対立を強めていきます。信徒を統率するため、各都市区には教会が置かれ、教会長は、カトリック教圏では司教、正教圏では主教と呼ばれました。3世紀に入ると、ローマの司教が、イエスの第一使徒であるペテロの後継者であることを理由に、すべてのキリスト教会を統括する最高権威者であることを主張し出します。一方で、西側の政治権力は失墜傾向にあり、476年のロムルス・アウグストゥス帝を最後に皇帝不在となったことから、東側の統治下に入ります。事実上の西ローマ帝国の滅亡という事態を迎えながらも、ローマの司教は、「ローマ教皇=パパ Papa」の称号を用いて自らの立場を主張し、ローマ全域に対する権力を獲得しようとしていったのです。
東ローマ帝国では、首都・コンスタンティノープルの主教が代々、東側の皇帝と力を合わせ、ビザンツ帝国を確立させ、領土をイスラム圏にまで広げます。最盛期は、6世紀のユスティニアス帝の時代。公用語としてギリシア語が採用され、ヘレニズム(※)的色彩の強い東側では、「ギリシア正教会」が確立されるに至ります。
※ヘレニズム(オリエントとギリシアの融合の意)
ローマ教皇(Papa)は、もはや、皇帝の権力に依存することはなく、宗教的な立場から主導権を行使し続け、ゲルマン人、ケルト人へも布教活動を行い、少数民族を吸収し勢力を拡大していったのでした。800年には、西側で統一されたフランク王国のカール/シャルルマーニュ大帝を、新しく西ローマ皇帝として擁立したことから、ローマ教皇とビザンツ皇帝との関係には決定的な亀裂が生じます。1054年、ギリシア正教会は、正式にローマ教会から分断を宣言。以降、ヨーロッパにおける教会大分裂時代を経て、カトリック教会は17世紀に「ローマ・カトリック教会 Ecclesia Catholica Romana」を正式名称とし、ペテロの後継者たるローマ教皇への忠誠心と、彼らの支柱となるカトリックの教義を主張して現在に至ります。
関連アルカナ・隠者
隠秘
近年アルカナ「隠者」に描かれている老人は、隠秘(オカルト Occult)の達人、熟達者を示して描かれることが多いようです。
そもそも隠者とは、俗世間との交わりを絶ち、隠遁生活を送りながら精神修行を積む行者を指すことばですが、ここから西洋の「オカルト」に相当する日本語の「隠秘(オカルト)」が導き出されたのでしょう。隠秘とは、文字通り、隠された世界の神秘を論じる分野の総称です。現実、日常とは一線を画する目には見えない不可視の世界、心霊、魂、宗教を扱う、いわゆる精神世界と呼ばれる領域だと考えてよいでしょう。超常現象という分野も含まれ、魔術、錬金術、占星術を時に含みます。
古代ギリシアにおいて、「ヘルメストリスメギストス Hermes Trismegistus」という架空の存在が、新プラトン派により生み出されています。エジプトの学問の神トートと、ギリシアの知恵の神ヘルメスの融合として、ヘルメスよりも三倍賢く偉大なる者と命名されたこの存在を、今日では、隠秘学の元祖と見なす人も存在しています。そしまた、ヘルメストリスメギストスにアルカナ「隠者」を見るタロット研究家もいるようです。
※ヘルメストリスメギストスの図版を入れたほうがよいか?
精神
「隠秘」の定義は、各所で様々だという節もありますが、「新興宗教Alternative Religion」を含める考え方もあります。また、神智学協会の創始者ブラヴァツキー夫人が提唱する「オカルト・サイエンス Occult Science」も、内容的には一致するようです。それは、物質的、また、サイキック的、メンタル的、霊的な自然の秘密を探る科学で、ヘルメティック科学ともエソテリック科学とも言われることがあるもの。カバラなどの神秘思想、魔術とヨガも含めて考えてられています。
最近では、「精神世界」と表現されることもあります。精神、心、感情といったことばは、普段何気なく、同義語として区別せずに口にされがちです。精神、スピリットspiritとは、心の一部であり、感じたり、思考したりといった通常の心の働きを越えたところで、さらに機能する部分だと言えるでしょう。例えば、理想を思い描いたり、理念を抱いたり、本能として感じたことを、理性的な振る舞いに転化する働き、それを司るのが精神です。むろん、心と精神の役割分担は重なる部分もあり、きっちり線引きができるものではありませんが、要するに、より人間的、理性的な人の振る舞いに通じていくものが精神の働きです。そして、日常ではなく非日常、目には見えない不可視の領域、死後の世界、霊界といった事柄を意識し、感知する部分でもありますが、これはまさしく、隠秘の領域です。ここから「精神世界」ということばが世間一般にも流布していったようです。今や、世界中で慢性的なスピリチュアルブームと言えるでしょう。ひとことでスピリチュアルと言っても、心霊、前世、来世、超常現象、宗教や神秘思想、占いまでも包括され、汎用性の高い市場にもなりつつあるようです。
隠秘、オカルトということばを初めて耳にする人に、こういった複雑な話題を取り上げることはせずに、「隠者」について、それはいわゆる「仙人」であると解説することも筆者はあります。
六芒星
隠者が灯すランタンの中の六芒星は、上向きの三角形と下向きの三角形が重なった図形です。錬金術においては、上向きの三角形が火と熱、下向きの三角形が水と湿を示します。これが重なった時、それぞれの三角形に横一本の傍線が入ります。横線が入った上向きの三角形が空気、横線が入った下向きの三角形が地を表すものでもあり、結局、二つの三角形が重なり合うということは、賢者の石の精製における四大要素の合一を表すものとなります。さらにこれを円で囲んだ図形は、「ユニバーサル・ヘキサグラム」もしくは「マルティネス・ヘキサグラム」と呼ばれ、最強の魔術的記号とされ、現代においても魔術愛好家の間で尊ばれているものです。
「マルティネス・ヘキサグラム」とは、聖マーティン「未知の哲学者;フィロゾフ・アンコニュ」とも呼ばれたフランスの形而上学者にちなんだ呼び名です。彼は、自由と博愛を啓蒙する秘密結社・フリーメイソンのシステムに哲学的な特徴を与えた人物であり、神智論者でもありました。ウェイト博士によれば、「賢者の石を手にした」彼は、秘伝を覆い隠すことに重要性を置かず、むしろ、一般の団体のほうが、独自の教義やシンボルについて公開したがらないのが常であると語っています。しかし、それら特定の団体・シンボルが、真理そのものではないのです。団体に属すること、シンボルを手にすること、身につけることに執着すれば、求道から逸れて魔道に陥るだけであるとも、”The Pictorial Key to the Tarot”の中では語られています。
ウェイト版のアルカナ「隠者」に見られる六芒星は、光です。これ以前の、アルカナ1から8に至る精神的徳性を獲得し、ようやく手に入れることができた宇宙創造と破壊のエネルギーを、小さなランタンに封じ込め、明るく美しく灯していようとするところに、「隠者」の新しい徳性を見出したいところです。旧約聖書の創世記において、主は最初に「光あれ」ということばを発しています。キリスト教的な神に捧げるべき美徳、神に仕える者として備えているべき美徳、即ち顕教的な美徳の影に隠れ見えなくなっていた、秘教的な徳性がここに描かれているのです。
「精神世界」とは、眉唾物だと言われがちです。しかし、この非科学的な世界だからこそ、複雑で割り切ることのできない人間が抱える問題に一抹の光を当てることができるのです。むしろこの分野において、人間の本質的な部分、その人なりの真理が浮き彫りになるという事実は、いつの世においても変わりはしないのです。
関連アルカナ・運命の輪
四聖獣、エゼキエルの幻視、不動宮
エゼキエルの幻視
ウェイト版に見られる有翼の四聖獣、鷲【わし】、獅子、牡牛、人間は、どれも皆、人類史に深く関わるが故にシンボリズムにおいて重要な生き物です。たてがみがある獅子はむろん牡獅子ですから、おそらく四聖獣はすべてXY染色体を持っているということなのでしょう。
野生の王者・獅子と天空の王者・ワシは、今日では世界各国で家紋、エンブレム、商標に取り入れられています。
旧約聖書の「エゼキエルの幻視」に、アルカナ「運命の輪」に登場する聖獣が見られます。そこには、予言者エゼキエルが、古代都市バビロンに強制移住させられ捕虜となっていた間に目の当たりにした、神と天使の情景が記されています。神の玉座を担【かつ】いで登場した天使は、顔面に羽が生えた智天使(ケルビム)であり、その様相は次の通りでした。
「・・・4つの生き物の形が出てきた。その様子はこうである。彼らは人の姿をもっていた。おのおの4つの顔を持ち、またそのおのおのに4つの翼があった。その足はまっすぐで、足のうらは子牛の足のうらのようであり、みがいた青銅のように光っていた。その四方に、そのおのおのの翼の下に人の手があった。この4つの者はみな顔と翼をもち、翼は互いに連なり行く時は回らずに、おのおの顔の向かうところにまっすぐに進んだ。顔の形は、おのおのその前方に人の顔を持っていた。4つの者は右の方に、ししの顔をもち、4つの者は左の方に牛の顔をもち、また4つの者は後の方に、わしの顔を持っていた。」
いかがでしょう。人の姿をしながらも、人、獅子、牡牛、ワシの4つの顔面を持つような天使を描くこととは、ことさらに至難だと想像のつくところですが、16世紀のイタリアでは天才・ラファエロがこの情景を見事に描き出しました。
※図版挿入 エゼキエルの幻視 ラファエロ 1518年
エゼキエル書ではさらに、この4つの生き物のいるところに輪があり、火を吹く車輪のようであったと語られております。この生き物たちの頭上の大空にサファイヤのようなものが現れ、王座と神を見ることになるのです。
主はエゼキエルに対して、予言者として滅びゆくイスラエルへ出向くことを命じ、手にしていた巻物を食べさせます。人は、字面【じづら】を目で追い、理解したつもりになるものですが、主の「食せ」という命に従い、エゼキエルは巻物の御ことばを飲み込んだのです。
智天使・ケルビムの顔面に表された四種の生き物、人、獅子、牡牛、ワシは、キリスト教において四福音書のシンボルでもあり、また、福音書を記した四聖人、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネをそれぞれ表すものでもあります。
獅子
ここで再び、何故これらの生き物が特別視されるに至ったかを考えてみましょう。この四種は、史上最高にして最強の存在であることに注目してみて下さい。強さにおいては、筆頭に上がるべき百獣の王である獅子は、その風貌から古来、「力」の象徴そのものであり、神殿や王座を守る役割を担ってきたものです。黄金のたてがみをたなびかせる「百獣の王」、見る者に畏怖の念をわき上がらせる獅子を太陽と王権の象徴と見なした人々は、古代エジプトの民だけではありません。日本では、神社の入り口に対になって置かれている狛犬が見られますが、もともと仏像の横に置いた一対の獅子の置物が起源のようです。
牡牛
肉食動物である獅子に対して、草食動物の牛は、獅子と異なり人間の生活に密着した存在であり、野獣の王に対して、家畜の王とでも言えましょうか。
エレメント(四大、四要素)において地の象徴とされる牡牛について、聖書においては、ヘブライ語のタウルス、英語のox、bullとして記されている牛は、古代人にとって、自家用車であり、戦闘機でもあり、肉や(雌牛であれば乳も)をも提供してくれる、最も価値ある重要なもの、財産そのものだったのです。牛は、神への最高の奉納物とされ、死者の棺に入れられることもあり、弔いの儀式は牛車の出番でした。
鷲
四聖獣の中でも高みなる存在、至高の聖獣とされるのがワシ。エジプト人達にとって、翼を有し天空に舞う鳥は天の御使い、天使、エンジェルにも相当します。原初の神・アムンはワシ神、あるいは鵞鳥(ガチョウ)として崇拝されていました。「死者の書」の中では、「ガアガア鳴く大きな鳥」によって、原初の混沌を象徴する沼の茂みに世界卵が置き去さられたことが宇宙の起源として記されています。また、エジプトでは初期の宗教書の中で、名もない神々が単に「ba バー」と呼ばれる人間の頭と鳥の身体を持った姿で描き表されているとのこと。ba バーは、王(ファラオ)の権威と結びつくようにもなります。エジプトの神々の王冠には羽根飾りがついているものが多く、一枚の羽根を象った大きな冠がアムンに見られます。主神として知られるホルスは、天空神としてタカの頭を持つ姿で描かれています。
人間
空において最強の猛禽類、ワシ、その下に最強の肉食動物、獅子、その隣に最強の草食動物、牛、そして、その上に三種の生き物を統括し得る存在として、人がウェイト版には描かれています。野生の生き物は、同類でなければ共存することが難しいでしょう。人の制御があって、それぞれの生き物が地上における各々【おのおの】の本分を果たすことが可能になるのです。
西洋占星術においては、理知を司る風のエレメントである三星座、双子座、天秤座、水瓶座のシンボルが、ヒトもしくはヒトが使う道具で表されています。
四聖獣と不動宮
これら「四獣の概念」の起源はエジプトに遡ります。ホルスの4人の息子たちが、それぞれハヤブサ、ジャッカル、サル、人間の頭を持ち、強き力ある者として、東西南北の4つの基本方位を司っていたのです。この4つ組の概念は、ギリシアに入って「テトラモルフ Tetramorph(『四重の』の意味」と呼ばれるようになります。人間の感覚的要素を示す獅子、肉体的要素を示す牡牛、高度な精神を表すワシ、これら三つが統合された精神性を示すものとして翼を持った人が象られたものであるのが「テトラモルフ」なのです。
参考図版「オカルトの事典」青土社中の図 九世紀の「アーマ書」ダブリン、トリニティ・カレッジ所蔵)
これらの生き物はそれぞれ四大を象徴してもいます。四大とは、B.C.5世紀前後、ギリシアの哲学者エンペドクレスが提唱した、万物を構成する4つの根(リゾマータ)、即ち、四大要素の「火地風水」に当たります。ひとつの根(要素)は、さらに「活動、柔軟、不動」の三種に分けられ、その中の「不動」に属する十二宮が、金牛宮、獅子宮、天蠍宮、宝瓶宮の四宮であり、いわゆる不動四星座が、ここに図像化されているのが興味深い点です。ホロスコープという仮想天球図上では、この四宮が示されている四点をつなぐと、円が垂直に縦横の線で区切られます。円の中に十字が描かれるように、90度間隔に配置されていることがおわかりいただけるでしょう。これが、いわゆるグランドクロスと呼ばれる座相です。グランドクロスは、活動宮、柔軟宮をつないでも形成されますが、不動宮のグランドクロスは、他の二種とは一線を画する強力な座相であるとされています。
関連アルカナ・死に神
エジプト死者の書、魂の裁量、天秤と剣
死者の書
エジプトに統一国家が誕生したB.C.3000年頃、中王国時代のパピルス紙製の出土品。そこには、人が死後、肉体から抜け出し魂と化し、来世に入って永遠に生きるという来世信仰について、また、死者を復活させる儀式、呪文などが多種多様な形で記されています。当時のエジプト人が未開の地で、正体のわからぬ自然の摂理や人間の生と死という定めを克服し、幸せに生涯をまっとうしようと全身全霊を傾け、書きつづられたものであり、彼らにとっては、生きるための指南書に等しいものとして、広く流布したことでしょう。現代に生きる私たちからすると、まるでSFファンタジーさながらに神や死後の世界を人の魂が旅するストーリーがつづられているもの。ここに描かれている「魂の裁量」の挿し絵は、広く世に知れ渡っています。生前の行いの裁きの構図、それが「魂の裁量」です。
もともと、古王国時代においては、国王ファラオやその一族といった身分の高い者だけに、「死後の世界と永遠の命」が与えられていたのですが、次第に、一般庶民の間にも広まり、いつしか、生前の行いにより「善良」だと神に認められた者には、来世への入場が許されるという観念が作り上げられたのでした。
魂の裁量
※図版挿入?
「死者の書」によれば、死者は、主神オシリスの前で、魂の秤量の儀式を通過することになります。裁量には、女神マート、もしくは彼女に仕える聖職者が持つ天秤が使用され、片方の受け皿には死者の心臓が、もう一方の受け皿には、法と真実の象徴である鳥の羽が一枚乗せられ、二つの受け皿が釣り合うかどうかが試されます。釣り合うということは、その心臓を有する者が「正しい」ことの証であり、その人物はその後も死者の楽園で暮らすことの認定を受けるのです。受け皿が釣り合わなかった者は、悪しき行いをした証であり、それによって、心臓を失い、死者の楽園に入る道を閉ざされてしまいます。死後の世界へ行く資格がないと判決を下された死者の心臓は放り出され、その心臓を、冥界の守り神アムムト(死者を喰らうもの)に食い尽くされてしまうという、エジプト人の死生観が凝縮されたかのような構図です。
「命はこの世ばかりのものではなく、善良であればあの世においても幸せになれる」という、古今東西の多くの宗教が提唱している教えの根本原理を垣間見ることができます。
天秤と剣
エジプト人伝来の「魂の裁量」の図像は、現在でも広く世に知られている名画に見ることができます。
※図版挿入?
片手に剣と天秤を持つ大天使ミカエル
ギリシア神話の裁量の女神
西洋占星術においても、12星座のひとつに「天秤」をシンボルとする、天秤座が配置されています。西洋占星学における天秤宮は、黄道十二宮の第七室に位置し、春分点を基点として始まる白羊宮とちょうど180度の対角を成しています。この宮が司るのは、人間の二元性、即ち肉体と魂、自然体としての生き物の部分と霊が司る理性的な部分との均衡、それによりバランスが保たれている人間の姿です。天秤座の性質として、本音と建て前を上手に使い分け、見た目や表面上の事柄にこだわり、美しく洗練されたものを好むというものがあります。他者を推し量りその重さに合わせて臨機応変に対応できる力にも優れています。興味・関心が、自己に向くよりも他者に向かってゆくため、外向性を示すことにもなります。
今日、私たちが世界各国の至るところで、「法」の象徴として用いられるシンボル「天秤」「剣」を目にすることができます。そこには、清く正しく善良でありたいと望んだ古代エジプト人の魂を、平和に生き、安らかな最期を迎える事を祈願した彼らの存在が未だ息づいているのです。
ウェイト博士が、アルカナ「正義」を作成するにあたって、人間の本性をどうとらえていたかは疑問ですが、この世の中に法や監視と取り締まりの機構がなければ、楽なほうへ流されがちな私たちが秩序を維持してゆくことは不可能に近いことでしょう。
錬金術
化学変化を用いて物質を混合、精製しながら金に変えようとする試み、金属変成術であり、その探究過程において、物質は「賢者の石」とも呼ばれています。物質のみならず、人間の内面的な精製作業、即ち霊的向上が目的とされることもあります。練金術の作業の片鱗は、既に古代エジプト、ギリシアの文化に垣間見ることができ、伝説上の隠秘学の始祖、ヘルメス・トリスメギストスの奥義であるとも提唱されていました。中世ヨーロッパにおいて爆発的に流行し、実際に、化学物質を用いた練金作業が行われ、その成果が化学の分野で学術的な功績と化していたのでした。錬金術師は、スイス、ベルギー、チェコなどに多くみられ、医師でもあるパラケルススは、硫黄、水銀、塩の三元素によって、四大要素である火、地、風、水が生まれるという、錬金術の体系を確立したことで有名です。
心理学者ユングは、錬金術を心理学的に説いた史上初の人物です。ユングが確立した精神療法の体系「精神分析」について、「自己の中の対立要素を統合させ、人間の再変成・個性化を実現させること」であるとして、錬金術との等価性を世に提唱しました。
黒化
錬金術において物質を精製する過程は、鳥の変成によって表されます。カラスが白鳥(白化)へと昇華し、不死鳥へと生まれ変わり(赤化)、そして生まれた卵から「賢者の石」が取り出されるという一連の象徴的な図像の中の「黒化 (ニグレド)」に相当するものとして、アルカナ「死に神」をとらえてみるのもよいでしょう。
「黒化」は、浄化が必要な錬金術師の状態であり、「腐敗、骸骨」という図像的なモティーフにより表されます。心理学者ユングは、この「黒化 (ニグレド)」を、アイデンティティが無意識になる時に心的生活が停滞することと同一視し、クライアントの個性化のひとつのプロセスであると考えました。彼の精神分析において「魂がない段階」、つまり自意識が崩壊した統合失調症の状態なのです。精神分析医の仕事は、錬金術師同様、魂を浄化させ心的生活の「復活」を促すことにあるとユングは解説しています。「死に神」は、生物学的、医学的な「死」よりも、一時期仮死状態になる人の生き様の表象であるととらえることができるのです。
死して再生するオシリス、キリストの復活等、神話や伝説における聖者の死と復活は、肉体との決別、より高次の力を備えた新たな存在へと変成をとげる儀式のようなものとして描かれるのが常。「死に神」が、死であり消滅の札でありますが、22枚の大アルカナの最終札ではなく、ちょうど中間地点に位置していることもわかるように、ここは折り返し地点。ターニングポイントと解釈するに相応しい切り札なのです。
関連アルカナ・節制
三美神
「三美神」は、ヨーロッパの画家たちに好んで取り上げられたテーマです。ギリシア・ローマ神話の「花」「喜び」「輝き」を司る三女が描かれているものもあれば、「美」「愛」「貞節」を擬人化し寓意的に描いたものもあります。三人の女性たちは、手を取り絡め合いながらも、どこか突き放し合っているようにも見えます。美しい乙女たちの姿に一瞬心を奪われますが、身体の線筋肉の動き、視線、ポーズなどから、彼女たちが互いに相容れない要素を持ち合い、完全な調和をなす事はできない事実と一種の葛藤を垣間見るに至るのです。完全なる美徳を有した完全な人間というものは存在せず、互いに補い合うことができた時に、人として真の輝きを発することができるのだという儚く悲しい現実をどう美しく描くか。画家の腕の振るい所であったことでしょう。
※参考図版 ラファエロ「三美神」
三対神徳
そもそも、キリスト教において、神という存在に向き合うために人間として求められる3つの徳性、三対神徳、「愛徳 Caritas(Charity)」「信徳 Fides(Faith)」「望徳 Spes(Hope)」が提唱されており、これらが現存する最古のタロット、ヴィスコンティ・キャリー・イエール・パックに含まれていることは興味深い点です。
キリスト教の「三対神徳」とそれぞれのシンボル
- 愛徳 乞食への施し、子供に授乳する母親
- 信徳 十字架、聖書、十戒の板、巻物、鳩
- 望徳 両手を合わせて視線を上部へ向ける、王冠、神の手
キャリー・イエール・パックの中の三つの札は、ヴァージョンを追って、下記のように変わっています。
「愛徳・慈愛」 → 「女教皇」
「信徳・信仰」 → 「恋人たち」
「望徳・希望」 → 「星」
小アルカナの杖、杯、剣、護符も、宗教的な聖物であることから、タロットと宗教との関わりは今後の研究課題と言えるでしょう。がしかし、ヨーロッパの歴史そのものが宗教史の土台の上に展開されているものであり、当時の文化、芸術品に宗教色が色濃く反映されているのは、ある意味当たり前のことでもあります。タロット22枚のアルカナを作成するに当たって、一部に表現のスタイルとして、キリスト教美術の姿を拝借したというだけのことなのかもしれません。いずれにしても、そういった疑問点や不透明な点を追求するのが研究家の仕事です。
七つの美徳
キリスト教においては、神に向き合う際の神学的な美徳である「三対神徳」に加えて、人間としての基本的な四つの徳「四枢要徳」を合わせて、七つの美徳を提唱しています。
- 愛徳(Charity)
- 信徳(Faith)
- 望徳(Hope)
- 賢明(Prudence)
- 剛毅(Fortitude)
- 正義(Justice)
- 節制(Temperance)
4世紀のアンブロシウス司教、6世紀のグレゴリウス教皇により、枢要徳の中で「節制」という徳性がキリスト教の要とされました。13世紀のヨーロッパ騎士道においても「節制」は尊ばれます。11~13世紀に建てられたフランスのシャルトル大聖堂には、「信徳、望徳、愛徳、質素、賢明、謙虚、剛毅、温順、和合、恭順、忍耐」という11の美徳が、それらと相反する悪徳と戦うモティーフで描かれた絵画が飾られています。ここには、「節制」「正義」が見られません。キリスト教における重要な徳目とは、当時の教説に関連し、時代と共に変化しているのでしょう。
四徳【しとく】
中世ヨーロッパ社会では、「賢明(Prudence)」「剛毅【ごうき】(Fortitude)」「正義(Justice)」「節制(Temperance)」の四徳が、人間の基本徳性であるとして尊ばれました。それぞれが、アルカナ「隠者」「力」「正義」「節制」に表されているものだという説をご存知の方も多いでしょう。この四枚に限らず、タロットの大アルカナ22枚それぞれに徳性が暗示されているものであるということができることを、本書では、力、正義の項でお伝えしている通りです。
ルネッサンス期に流行した、徳についての作品には、ローマの哲学者ルキウス・アンナエウス・セネカ(Lucius Annaeus Seneca)の『幸福な人生について』などがあります。
関連アルカナ・悪魔
半人半獣、ギガンデス
多くのタロットにおいて、アルカナ「悪魔」には、両性具有の半人半獣が描かれていることが常です。半人半獣といえば、本書でも古代エジプトのスフィンクスに触れました。私達に馴染みがあるのは、12星座の射手座になったケイローンなどでしょうか。ケイローンは、ギリシア神話に登場する半人半獣のケンタウロス族の一員で、上半身が人間、下半身が馬の姿をした馬人です。音楽の神アポロンと月の神アルテミスから教育を受けたため、他の馬人族とは一線を画する存在でした。音楽、医療、予言、狩猟の力を授かり、人間とも親しく付き合い、ペリオン山の洞穴でギリシアの若者を教育することもありました。武術を教えられた勇者ヘラクレス、医術を伝授されたアスクレピオス、馬術を伝えられたカストなどと、皆ギリシア神話における英雄的な存在にとって、ケイローンは掛け替えのない師であったのです。大神ゼウスは、この優れたケイローンを死後天界へ上げ、黄道十二宮の九室、人馬宮を司るように取り計らったのでした。
ギリシアにおいては、半身半獣の他に、多くのギガンデス、不自然な体をした凶暴性を持った生き物が登場します。獅子と山羊をつなぎ合わせたような胴体のキマイラは、それらの野獣性を備えつつ人間の知恵も授けられていたといわれます。同様に、スピンクスやタイフォンもギガンデスに属する半身半獣と考えてよいでしょう。タイフォンは、火を吹き台風を巻き起こすことで知られていますが、彼らを恐れ多くのギリシアの神々が一時エジプトに非難したといわれます。その時に、ゼウスは牡羊に姿を変え、エジプトの角を持つアムモン神として崇拝されるようになったと伝えられています。これはつまり、ギリシア神話復興後も、しばしばエジプトの神とそれぞれの逸話が世に流行することがあったということなのです。その都度、人々が表現する神の名前と形とに変容が見られるようになったのでしょう。
The Pictorial Key to the Tarotの中でウェイト博士は、タロットはエジプト象徴主義の代物ではないことを主張しており、エジプトのスフィンクス、そしてギリシアのテュポンを同時に描くという構図もその主張が表れているところなのではないでしょうか。
関連アルカナ・塔
ジッグラト
シュメール時代、メソポタミア諸都市において、「ジッグラト 聖塔 Ziggurat」なるものが建造されており、これが、いわゆる旧約聖書の「バベルの塔」の逸話の元になったものではないかと言われています。現在、ウルと呼ばれる都市遺跡に見られるジッグラトは、紀元前2050年頃に建造されたものを復元させたもので、ピラミッドを彷彿とさせる直線的な外観となっています。
※参考挿絵 山川出版社 世界史 資料集
関連アルカナ・星
星辰信仰
自然崇拝の一種、光、ないし光るものを神として崇め奉る「星辰信仰」は、文明の発祥と共に起こったものだといわれています。人類史を遡ってみれば、人々は神の物語を創造しながら、神の加護を得ようと、その存在の真実の姿に少しでも近づこうと祈りを捧げる毎日であったことがうかがわれます。その毎日の暮らしの中で、様々な物を測る尺度となった太陽・月の光の満ち欠け、星の軌道は必要不可欠なものであり、これらを応用した占星術とは、彼らの死活問題に関わる重要な道具であり技術でした。占術とは、有史時代に入って道具を手にした人が、同時に持ち得た最古の技術でもあるのです。
おそらく既に、シュメール人にも星辰信仰があったと推察できますが、彼らの信仰は地母神などどちらかと言えば大地に向けられる傾向にあったようです。
エジプトの文明において、人々にとって、光が厄災を避けるためのものであった記録が残されています。 来世信仰と共に発達し、人間の肉体は滅びても、魂は天空の星と化し、永遠に輝き続けると信じられていました。中でも天極に輝くひとつ星・北極星、一等星のシリウスが見られるおおいぬ座、オリオン座は、一年を通じて夜空に姿を見せていることから、不滅の象徴として彼らは敬意を払いました。
光、光明(こうみょう)
光、または、光るものは、神性、神的エネルギーの象徴であり、今日の私たちの生活においても、将来への明るい見通し、希望を示すものとして認識されています。仏教においては、智慧(ちえ)や慈悲の象徴でもあります。太古から「光」から始まった人、「光」が産んだ神についての神話が古今東西に伝えられています。
最大級の太陽は一者の神、創世主、父権などを表すものとされてきました。相対して、夜空の太陽と崇められた月は、非存在、不可視の存在、見えざる領域であり力であり、潜在性と母性の象徴とされる傾向がありますが、地域によってはこの太陽と月が象徴するものが逆転している場合もあります。星は、この太陽と月の申し子、大いなる父と母を持った私たちひとりひとりの輝き、浪漫を感じさせながらもどこからともなく生まれ消え行く儚い定めを背負った人の子の象徴です。20世紀最大といわれるオカルティスト、アレイスター・クロウリーのことば「すべての男女は星である」とは、彼の最大の功績かもしれません。
キリスト教においては、混沌を光と闇とに分ける神の創生作業から、天地創造の物語が始まります。星は、イコンの中で、聖母マリアの冠や衣服に見られます。また、12の星が描かれている時にはイスラエルの12部族、12使徒を象徴し、夜空に輝く無数の星はアブラハムの子孫、即ち神の申し子としての地上の民、信者ひとりひとりを表すものだともいえるでしょう。闇を制し光をもたらした朝日、明けの明星がキリストの象徴であるのに対して、聖母マリアは海の星として表されています。
いわゆる西洋占星術とは、個人の出生時の星の配置図、即ちホロスコープを解釈することから始まります。主要惑星と呼ばれる十の星の並び方で、その人のパーソナリティや人生傾向を判断する占いです。360度の円の中に、それぞれ違った影響力のある星たちが、どのように散らばっているかが描き出されたおのがホロスコープであり、この円の中で、惑星たちがそれぞれどのような角度を取り合っているか、その数値が重要な判断材料になります。ひとつの出生図はひとりの人間の人生縮図であり、大いなる宇宙の中の小宇宙であるとも解釈されるのです。
星
天空に輝く「星」は、太陽、月と並んで、太古より人が「神聖なる光」として崇める三光のひとつ。
ウェイト版アルカナ「星」の情景は、北極星を軸に、その周囲を回転してゆく北斗七星の7つ星、即ち大熊座が描かれたものであるとも、女神イシスの象徴・シリウスと、その周囲に輝くオリオン座が描かれているとも解説されてきました。北極星は、地球の自転軸の延長方向にあるため、通年真北見えます。故に、エジプト人によって不滅の象徴とされたのです。彼らは、この星を目印にして、方角や時間の経過について多くの情報を得たのでした。また、天空に輝く青白い一等星、全天で最も明るい恒星シリウスは、彼らにとって夜空の太陽とみなされました。ナイル川の氾濫を知らせる星として重要な役割を果たすこの星は、英知の象徴・女神イシスの星、その近くに付き添うように輝くオリオン座は、万能神オシリスの象徴とされたのでした。
アルカナ「星」には、不死鳥が描かれています。キリスト教美術では、生命の木にとまる鳥と木に絡み付く蛇とが戦う図像が、善と悪との戦いを象徴として描かれます。また、ペリカンは、イエス・キリスト自身を象徴する鳥とされています。自ら胸を突き流れ出た血によって、蛇に殺された雛鳥を復活させる図像が残されており、イエスの自己犠牲と献身を表すために描かれるとのことです。
関連アルカナ・月
フリーメイソン
フリーメイソンは、11世紀のヨーロッパの石工たちによって構成されたギルド(特権的同業者組合)が起源であり、今もなお、自由、友愛、平等の三精神を基本原理として掲げる博愛主義団体として存続しており、世界各地で「神性の追究、内的探求」をテーマに集いが開催されています。石工たちに不可欠な職人道具である、直角定規とコンパスがフリーメイソンのシンボルです。フリーメイソンにおける、コンパスと直角定規は、完全なる円と正方形、即ち、天と地の融合を示し得るものであり、また、コンパスが直角に開いて描かれる時は、肉体と精神が理想的な均衡を保っていることを示すものとされているとのこと。こういった図像解釈における定式は、中世以来近代にかけて成立したようです。
コンパス、全てを包括する宇宙、宇宙体系という論理的思考、人類愛、人類全体に広がる規範を象徴するシンボルとして、現在では全世界で広く使用されています。
※参考図:フリーメイソン関連の図版
エステンシ・タロットの月
エステンシ・タロットが世に出たのは15世紀。「月」は、人智の光、内光、Inner Lightの芽生えを象徴するものであるとして、コンパスを描き込んだ画家は、フリーメイソンの存在を意識していたのでしょうか。アルカナ「星」の段階で生まれた希望を、まだほの暗い地上でどう具現しようかと模索する人の意識が描かれているような札です。
関連アルカナ・太陽
太陽
シンボルの中のシンボル、シンボルの王者とも言える「太陽」です。太古において、万物の生みの親、唯一神と崇められたこの恒星は、数千年の時を経て今もなお私たちの頭上で生命の光を、生きとし生けるものに不可欠なエネルギー源としてさんさんと与えています。
エジプト神話の主神、太陽神ラー、ギリシア神話の英雄、太陽神アポロン、自らを「太陽王」と名乗ったフランス国王ルイ十四世等に見られるように、古今東西の人々にとって、太陽は普遍的な権威の象徴として尊ばれてきました。男性神、国王のシンボルとしての太陽はあまりにも私たちの意識に浸透しています。天空に輝くその熱と光が男性の血気と結びつけられ、対して、地上を潤す冷たく流動的な水、海、大地そのものは、女性の緒力と結びつけられ、その象徴を太陽と対の関係にある「月」としたのでした。
太陽と月
それぞれ相対する男性と女性の緒力を担うものとしてひとつの組みになり、ひとつの世界が形成されるという神話がよく知られていますが、時代や土地により太陽と月の役割が入れ替わっていること、月が男性神で、太陽が女性神であることなどは珍しくはありません。シンボルは、人の意識と感性により生み出されるものですから、時代と共に変化し推移してゆくものなのです。月を精神、心の象徴とし、対照的に、太陽を肉体、物質とするという定説は、一重に多くの人を説得できるものであったから、そうなっただけのことです。西洋においては、ギリシア神話が定式化の決定打になったように思われます。
そう定めることに利便性を見出した時の権力者たちに利用されてきたような節があるとしても、結果として多くの人々の心に受け入れられた説が、世代を通じて語り継がれ、人々の意識や生活に定着すること、これが「伝統」です。長い歴史を背負った、象徴、シンボルというものですから、端的に扱うことは避けたいものです。
太陽神を女性と見なす神話は東洋に限らず多々見られます。日本では、天照大神が奉られています。最初の神である「創世主」は、原理的に女性でなくてはならないとする説や、最古の神は天空よりも、豊穣を司る地母神であるはずだという人々のある意味本能的な感覚がそこにはあるのです。「太陽」に男性の諸力、絶対的権力、支配力を見るか、女性の諸力、宇宙の起源、命の源泉を見るか、そしてそれを男性に例えるか女性に喩えるか、各所の地域性にも関係するところでしょう。
太陽と馬
様々なタロットの中で、第19のアルカナ「太陽」に、馬に乗った幼児という図像を採用しているデッキが多々見られます。「太陽」は、文字通り日の出、生命力、出生と誕生の象徴であり、「死」の対極です。しかし、生と死は切っても切れない関係性にあり、あらゆる生き物が選択の余地のなく、負わなければならない運命なのです。その抵抗し難き波の勢力、抑えきれない生命力の凄まじさが、躍動する馬の姿に象徴されていることは、それが「生の札」であろうと「死の札」であろうと変わりありません。
何人も侵しがたい命の生誕と死。疾風(はやて)のように現れ立ち去ってゆく馬上の人間という構図に集約されるのでしょう。
関連アルカナ・審判
最後の審判
通常、審判とは、規則、戒律、ルールに基づき何らかの案件を審議し判定を下すこと。法の下における裁き、律法、公正な判断を示すアルカナとして「正義」を介しましたが、これとは違ってこの第二十番目のアルカナに描かれているのは、キリスト教における「最終審判」であることに着目して下さい。即ちそれは 「公審判」「世界審判」と呼ばれるもので、宗教事典によれば、世界の終末に全人類が受ける神の裁きと定義されています。他方、個人の死後、生前の行いが裁かれることを「私審判」と言います。こちらは、一個人が死後、生前の行いについて神から受ける裁きを指します。いずれにしても、身近な裁判所で執り行われている真理とは一線を画すものです。
終末思想とヨハネの黙示録
私たち人類が最期を迎える時がいつか訪れるという観念は、宗教上の考え方としては、珍しいものではありません。新約聖書に見られる「ヨハネの黙示録」は、イエス・キリストの弟子ヨハネが、イエスにより受けた啓示、及び幻視が書き記された章であり、世界で最もよく知られている人類滅亡の様相がつづられた作品だと言えるでしょう。
ヨハネの黙示録のあらましは以下の通りです。
イエスの第一使徒とも言われるヨハネは、死後復活したイエス・キリストの霊によって、各地の教会に信仰心が薄れていくことに対する警告の書状を送るよう命じられます。その後、天の門が開き、ラッパのような呼びかけの声と共に、これから起こるであろう事柄を見せられるのです。神の御座には、碧玉や赤瑪瑙(めのう)のように見える神と、その周囲を取り囲む24人の長老たちが見られました。御座では、神の7つの霊が炎となって燃えさかり、御座の前には水晶のような海が広がり、さらにその4つの生き物、それぞれ獅子、雄牛、人、鷲のように見え、6つの翼を持ち全身が目で覆われている生き物がいたのです。御座と4匹の生き物との間に、ほふられた小羊がいました。7つの角と7つの目を持ったその小羊は、全世界に使わされた神の7つの霊の表象、これがイエス・キリストの姿だったのです。
小羊が、神の手にある巻物の7つの封印のひとつを解くと、4つの生き物の一匹が「来たれ」と叫び、その度に、白い馬、赤い馬、黒い馬、青白い馬と総勢四種の馬が、神の御怒りの報復に出るのでした。ここからが地上の最期です。神の最終審判とその結末の下りへと移項します。
この後、7つの教会、7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢が登場するところなど、「黙示録」においては、4と7という数字に重要な暗示が込められていることが分ります。これらの象徴や数をどう読み解くかという分野は黙示文学と分類されています。
異教徒、キリスト教を弾圧する者たちによって荒らされ汚【けが】れた地上を成敗(せいばい)するが如く次々と神の御使い、天使が現れ、それぞれがラッパを吹き鳴す度に地上が焼け、徐々に人々を死に至らしめてゆくことになるのでした。7人の御使いが登場し、各々が手にしていた神の怒りに満ち溢れた鉢、7つの災いの満ちた鉢を大地に、海に、空に傾け、いよいよ世界は終わりを迎えます。
しかし、この人類史に最期の幕が下りる前に、神はひとつの仕掛けをしていたのです。神を信じ教義を守り抜いた敬虔な信徒は既に選別され、その名を巻物に記していたのです。最後に封印が解かれたこの「いのちの書」に名前が上げられていた者は、神の救済をここで得るのです。荒れ果てた天と地が消失すると同時に、新しい天地が創造されるのでした。
アルカナ「審判」と終末思想
アルカナ「審判」を、必ずしもある種の思想・宗教上の教義を前提に解釈する必要はありません。あらゆる生命体に共通していることは、生まれてそして死んでいくことに尽きます。生と死は、私たちの根幹的なテーマです。「私たちは何故生まれてきたのか、死んでどこへ行くのか」という問いに対して、万人を納得させる回答はあり得ません。それでも人はそれぞれその人なりに、人生のある地点で答えを出すのではないでしょうか。年齢を経て、その答えが移り変わっていく場合もあるでしょう。私たちが追い求めなければならないテーマであることを、象徴的にそこに見ます。
目には見えない不可視の世界について、死後の世界について、善悪の戦いと勝敗についての観念がどれだけ物語にドラマに絵画に映像になって、私たちの振る舞いから内面的な情動までを、日常生活を刺激しているかを考えてみましょう。幼い頃に好むと好まざるとほぼ無意識の内に目にし、耳にする童話、古今東西で語り継がれるおとぎ話の多くが、懲罰的な死を説き、純真無垢な精神性が報われるストーリーに終始しているではありませんか。たとえ、特定の神仏に信心していなくても、死後の世界、「公審判」の存在を意識している人達の数が圧倒的多数を占めていることは事実でしょう。
アルカナの連続性札番号により連続性のある解釈が結びつけられることがありますが、肉体が生誕する「太陽」から、死者の生まれ変わりを示す「審判」の二枚をつなげて意味のある解釈を求めるのは、一種無理がある作業ではないでしょうか。むしろ、生まれ変わった新たな新生児としての魂を「審判」に見出すことで、19番と20番の二枚の札をそれぞれ肉体と精神における等価的な象徴と判断するのが妥当だと、筆者は考えています。
関連アルカナ・愚者
愚者の風貌
杖の先に荷物をぶらさげて肩にかけ、旅をしているのが典型的な「愚者」。「狂人matto」「こじきbeggar」なるタイトルがつけられ、みすぼらしい男性が描かれている一方、ウェイト版に見られるように、「無防備な冒険者」が描かれているデッキも現在出回っている中には多いようです。
若者か老人かに二分するようですが、「旅人」「風来坊」を思わせる絵柄に「流浪の民としての人生」が暗示されている模様。ヴィスコンティ版「愚者」には、髭を生やしみすぼらしい衣服の下から肌着がのぞいているような、何とも貧相な、道化のようにさえ見える男が描かれています。往々にしてその人物の足に、犬、ネコ、ワニなど小動物が噛み付いている姿があり、それらは「人に守り神の存在があること」「人間の浅はかさや愚かさの異形」であるなど、表されていることには諸説あります。
トランプの「ジョーカー」を彷彿とさせる様相も特徴的ですが、トランプにジョーカーが加えられたのは、タロットの発祥よりだいぶ後のことです。
愚者と狂人の擬人像
キリスト教美術の擬人表現において、1200年頃のフランス、パリのノートルダム大聖堂やアミヤン大聖堂に見られる「狂気」の擬人像が、古典的なタロットのアルカナ「愚者」を彷彿とさせるものであり、大変興味をそそられます。擬人像は、キリスト教における七つの美徳のひとつ「賢明」に対して描かれたものであり、ほとんど衣服をつけていない男が棍棒を持った姿をしています。その隣には「信仰」、それに対する悪徳「偶像崇拝」の擬人像などが並んで描かれています。
中世期ヨーロッパの物語の挿し絵に見られる狂人が、チーズなど食べものをくわえた姿で表されるのが一般的ですが、いずれも、ほとんど衣服をつけていない男が、周囲からの冷やかしやいやがらせを避けるために、護身のため棍棒を持ち立っている姿をしているのが特徴です。
他にも、この黄道十二宮の擬人像も見られ、
※シャルトル大聖堂の図版を入れたい
関連アルカナ・世界
タロットに見られる西洋文化
ヴィスコンティ版は、キリスト教色の濃いタロットとなっているようですが、そもそも当時創作された美術作品、絵画の大半がキリスト教をモティーフとしたものであることが、まず理由に上げられます。タロットという絵札の絵にも、時世が反映されて当然でしょう。活版印刷が発明される前の15世紀と言えば、書物も絵画も希少品でした。手にすることや目にすることができるだけで、それが一種のステイタスだったことが推察できます。それらの大半が、キリスト教文化の担い手たちによって生み出されたものでありました。言い方を変えれば、文化・教養の一環、たしなみのひとつとして存在するアカデミックな素材は大抵、キリスト教に関する代物であったのです。当時のヨーロッパ社会では、ヴィスコンティ一族のみならず、あらゆる貴族、上流階級の人々が、彼らの信心深さの如何に関わらず、一種義務教育として聖書を読み、宗教画を鑑賞してきたわけです。ヨーロッパの政治経済、歴史に携わる諸侯一族にほどこされた、いわゆるエリート教育そのものが、キリスト教色に色濃く染まっていたのです。この時期作成されたタロットに、文化と教養のベースであった宗教的なモティーフが多く取り入れられている所以がおわかりいただけたでしょうか。
占術家の冠、私たちに内在する「女神」
ウェイト博士は、描かれているリースを「占星術師の冠」であるとし、リースの中で踊る女性を、宇宙の神秘を知るに至った時の私たちの内的な光であると、アルカナ17「星」の女性の異形であると述べています。
アメリカ各地でのセルフ・ケア・ミーティング(自助グループ)において、会の始まりに皆と一緒に捧げる祈りのことば「SERENITY PRAYER」があります。
GOD, GRANT ME THE SERENITY
TO ACCEPT THINGS I CANNOT CHANGE,
COURAGE TO CHANGE THINGS I CAN,
AND WISDOM TO KNOW THE DIFFERENCE
神よ、静寂を呼び覚まし、私は求めます。
流れに逆らわず、宇宙に身を委ねようとする勇気と、
流さることなく、力の限り変化を起こそうとする勇気を。
そして、いずれにすべきか
その違いを知り得るだけの知恵を
ミーティングにおいては、「神」なる部分は、私たちに内在するHigher Powerであるという解釈がなされます。静寂の中で耳を澄ませれば、誰もがHigher Powerとの交信を果たすことができること、適切な道へ進み、救いが得られることを教えられます。私たちが生きている中で、直面する壁について、それを変えようとアクションを起こすべきなのか、受け入れるべき事態なのか、ある意味「妥協点」を知ることが折に触れて必要になってくるのです。伸【の】るか反【そ】るか、いずれかを問うために古来より伝統的に用いられてきたのが占術なのです。
私達には、サインが必要なのです。シンボルによって、そのサインを示してくれるのがタロットであり、私たちに内在するHigher Powerとの交信に匹敵することでしょう。タロット占術で導き出せる答えは、当事者の心の中にあるという人も多く存在します。当事者だからこそ、向き合いきれない心に対して働きかけ、円満な解決法を導き出す、それがタロット占術であることを伝えてくれる札、それが大アルカナ22枚なのです。